不倫相手への慰謝料請求を弁護士に頼みたいけど、
- 弁護士費用はいくらかかりますか?
- 相場はどれくらいですか?
- 安く抑えるコツはありますか?
この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。
不倫相手に慰謝料請求するにしても、請求書面を作ったり、話し合いをしたりと手間・暇がかかります。また、特に、話し合いや裁判にまで発展した場合の手続きを一人で行うことは負担が大きく、弁護士に頼みたいと考える方も多いと思います。
もっとも、その際に最も気になるのが「弁護士費用」のことではないでしょうか?弁護士費用は決して安い金額ではないことから、普段の買い物のように手軽にサービスを購入できるわけはなく、依頼をためらう方もおられると思います。
そこで、この記事では、かつて法律事務所で勤務経験のある筆者が弁護士費用の内訳を簡単にご紹介した上で、弁護士費用の相場や少しでも弁護士費用を安く抑えるためのコツなどについて解説していきたいと思います。
なお、配偶者と離婚する場合の慰謝料や弁護士費用の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
弁護士費用の内訳

一般的に、弁護士費用の内訳は以下の内容から構成されています。各内訳の費用が高くなれば、トータルでかかる弁護士費用も高くなります。
- 法律相談料
- 着手金
- 報酬金
- 日当費
- 実費
法律相談料
法律相談料は弁護士に依頼する前(正式に委任契約を締結する前)に、弁護士に相談した際に発生する費用です。
初回の法律相談に限り「無料」で対応している法律事務所も多いです。もっとも、無料であっても「1回限り」という回数制限や「30分まで」、「60分まで」などという時間制限を設けている場合がほとんどです。一方、有料の場合は、1回あたり「5,000円~/1h」が相場です。
着手金
着手金は弁護士に依頼した後に発生する費用です。
着手金は弁護士が業務に着手するためのお金で、緊急の場合を除き、着手金を支払うまで弁護士は弁護活動を始めてくれません。着手金を「0円」と設定している事務所もありますが、その場合は、後記の報酬金が高く設定されている可能性もあります。一方、金額を設定している場合は「10万円~」が相場です。原則、一括払いで、一度支払った着手金は弁護活動の成果にかかわらず返金されません。
報酬金
報酬金は「基礎報酬金」に「追加報酬金」の2階建て構造とされているのが一般的です。
基礎報酬金は「20万円~」が相場です。一方、追加報酬金は「獲得した慰謝料(経済的利益)の10~20%」などと、獲得した慰謝料に応じた金額を設定されます。そのため、獲得した慰謝料が高額となればなるほど報酬金(弁護士費用)も高額となります。
日当費
日当費は弁護士が事務所外で弁護活動を行った際に発生する費用です。
事務所外で弁護活動とは、たとえば、不倫相手との話し合い、調停・訴訟のための裁判所への出廷、などです。「示談交渉1回につき3万円」、「裁判所への出廷1回につき5万円」などと固定の金額が設定されています。事務所外での活動回数が多くなればなるほど日当費は高額となります。
実費
実費とは、その名のとおり、弁護活動によって実際にかかった費用です。
たとえば、書面の郵送費、事務手数料、交通費などがこれにあたります。実費も弁護士の活動内容が多くなればなるほど高額となります。弁護士費用といえば着手金や報酬金に目を奪われがちですが、日当費や実費も意外に高額となる可能性がありますので注意しましょう。
【ケース別】弁護士費用の相場

不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼するとしても、弁護士にどこまで依頼するのかによって弁護士費用は異なります。そこで、以下では、弁護士に「請求書面の作成のみを依頼する場合」と「請求書面の作成と示談交渉を依頼する場合」にわけて、弁護士費用の相場をみていきましょう。
請求書面の作成のみを依頼する場合
弁護士に請求書面の作成のみを依頼した場合の弁護士費用は「3万円~5万円(着手金)+実費」が相場です。
弁護士にとって不倫相手との示談交渉が不要で、報酬金が発生しないことから、弁護士費用は低額となります。なお、請求書面の作成のみの依頼を受け付けていない弁護士もいます。請求書面を送っただけでは不倫相手が素直に慰謝料を払うケースは少なく、示談交渉とセットで依頼することをすすめられることが多いかと思います。
請求書面の作成と示談交渉を依頼する場合
次に、請求書面の作成に加えて、不倫相手との示談交渉を依頼した場合の弁護士費用は「30万円~(着手金・報酬金)+日当費+実費」が相場です。
着手金は各事務所によって異なりますが、最低でも10万円~20万円はかかります。報酬金のうち基礎報酬金は、最低でも20万円~30万円はかかります。基礎報酬金に加えて追加報酬金も加算されます。不倫相手との示談交渉の回数、裁判の有無、期間・回数などによっては日当費、実費が高額となります。示談交渉で解決できたとしても40万円前後はかかると考えておいた方がよいでしょう。
弁護士費用を抑えるコツ
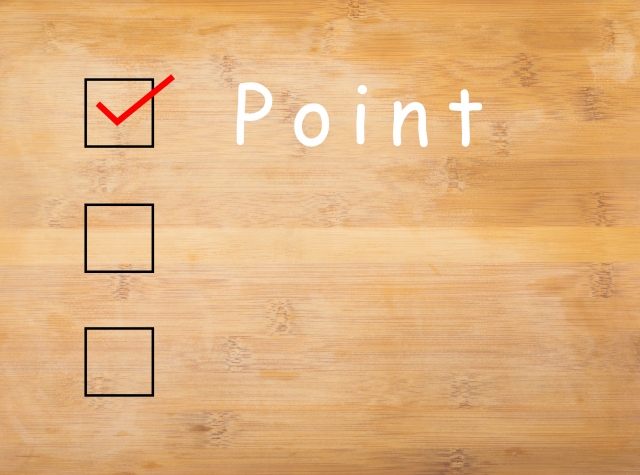
弁護士費用の相場の箇所でもおわかりいただけたように、弁護士費用は決して安い金額とはいえません。そこで、以下では、少しでも弁護士費用を安く抑えるコツをご紹介したいと思います。
自力で解決できないか検討する
まず、そもそも弁護士に依頼すべきなのかよく検討する必要があります。
不倫相手に慰謝料請求する場合は、必ず弁護士に依頼しなければならないというわけではありません。自分で交渉を行う自信がある場合や不倫相手が請求に応じるような状況であれば、わざわざ高いお金をかけて弁護士に依頼する必要はありません。もっとも、不倫相手が弁護士に依頼したり、交渉が失敗するリスクもありますので、自分で行うのか弁護士に依頼すべきかの見極めは慎重に行いましょう。
無料相談を活用する
示談交渉の切り出し方、進め方などで困ったら、無料相談を申し込んで弁護士に相談してみてもよいでしょう。
無料だからといって雑に扱われることはありません。多くの弁護士がどんな些細な質問にも誠実に答えてくれるでしょう。また、相談したからといって無理やり契約させられることはありません。近年は多くの事務所で無料の法律相談を実施していますから、時間の許す限り、できるだけ多くの弁護士に相談し、意見を聞いてみるとよいでしょう。
話し合いでの解決を目指す
もし、弁護士に依頼することに決めた場合は、話し合い(示談交渉)での解決を目指しましょう。
話し合いで解決できれば、着手金や日当費、実費を安く抑えることができます。話し合いでの解決を目指すには、不倫相手に話し合いを切り出す前に話し合いで解決してくれる弁護士を探し、依頼することです。もっとも、あなたが弁護士に依頼した結果、不倫相手も弁護士に依頼し、話し合いが泥沼化する可能性もあります。弁護士に依頼したからといって、必ず話し合いで解決できるわけではありません。
法テラスを利用する
最後に、法テラスを利用することです(利用条件があります)。
法テラスでは、主に「法律相談援助」と「代理援助」の2つの援助が用意されています。法律相談援助は、1つの法律問題につき1回30分の法律相談を3回まで受けることができる制度、代理援助は、弁護士費用を法テラスが立て替え、後日、分割で返済していく制度です。弁護士費用が安い上に、後払い、分割返済も可能で、生活保護受給者には返済の猶予あるいは免除制度も用意されています。
弁護士の探し方、選び方選ぶためのポイント
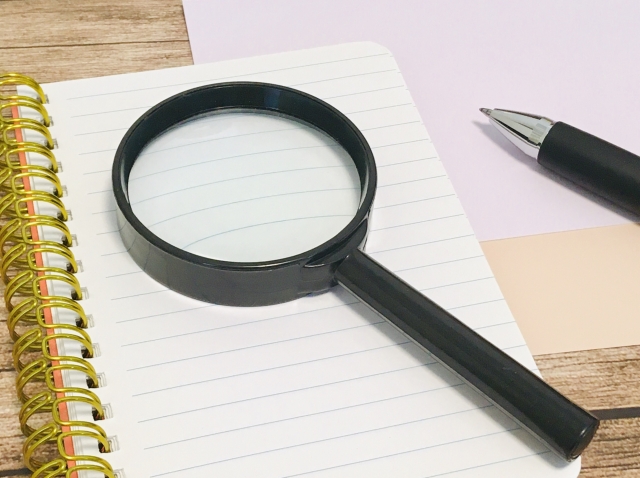
最後に弁護士の探し方について簡単にご紹介しておきます。弁護士の探し方はおおむね次の4通りです。
■ ネットで検索する
■ 経験ある知人から紹介してもらう
■ 市区町村が主催する法律相談を利用する
■ 弁護士紹介センターに申込む【東京限定】
また、弁護士を選ぶ際は次の点に注意しましょう。
【相談前】
■ 離婚分野を取り扱っているか
■ 弁護士の登録番号
■ 相談件数(処理件数)
■ 探偵と連携がとれているか
【相談時】
■ 相性が合うかどうか
■ 態度、話し方など
■ 協議(話し合い)での解決案も提示してくれるか
■ 弁護士費用について丁寧に説明してくれるか
■ リスク、デメリットも説明してくれるか
■ 相談の弁護士が担当してくれるか
詳細は以下の記事で詳しく解説していますので、よろしければチェックしてみてください。

